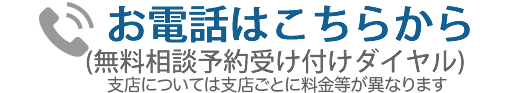2022.07.20
危急時遺言
弁護士 渡辺 菜穂子
通常の遺言形式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3形式のいずれかということは一般的にも知られていますが、このような通常形式以外に、特殊な事情のもとでは、簡易な方式での遺言が認められています。特殊な事情としては、民法上にいくつか定めがありますが、このうち一般危急時遺言(民法976条)について説明します。
目次
1. どのような場合に行うか
一般危急時遺言は、余命いくばくもない状態で、今すぐ遺言を遺さなければ遺言者がお亡くなりになってしまうような緊急事態において、遺言を遺す方法です。法律事務所で過去扱ったケースとしては、公正証書遺言の作成について依頼を受け、担当弁護士が準備を行っている段階で、遺言予定の方の容体が急変してしまう場合などに、危急時遺言の作成をするというケースがあり得ます。
一般危急時遺言は、通常の形式要件が緩和される代わりに、一定の形式要件を満たして作成される必要があり、また遺言後にも直ちに所定の手続を経ねばなりません。また、一定の場合に効力が失われることになります。
2. 法律上の定め
(1) 形式的な要件
ア 危急時遺言を行うその場での形式要件
① 証人3人以上の立会い
② 遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた証人が筆記
③ 筆記した⑵の書類を、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、閲覧させる
④ 各証人が、筆記の正確性を確認して⑶の書類に署名・押印
イ 危急時遺言後の手続要件
遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に遺言確認の申立てをする。
・立会証人または利害関係人が行います。
・家庭裁判所が、「遺言が真意に出たもの」という心証を得なければ、確認した旨の通知が行われません。
(2) 失効
遺言者が危篤状態から持ち直し、通常の形式で遺言ができるようになってから6か月間生存する場合には、一般危急時遺言は失効します。
3. 具体的な流れ
(1) 段取りや証人の確保
危急時遺言が行われる場は、多くは、遺言者が危篤やそれに近い状態となっているので、病院におられるケースが多いです。プライバシー等の観点から、個室や他に誰もいない部屋を病院に確保してもらう必要があります。
また、利害関係のない証人3人が必要です。一人は、作成の委任を受けた弁護士が担当するケースが多いでしょう。もう1人は、ケースワーカーや医師等、遺言者の意思状態を客観的に確認できる第三者が望ましいです。それ以外は、ご親族等から選んでいただいて構いませんが、推定相続人・遺言により財産を受ける人やその配偶者・子・孫、未成年者はなることができませんので(証人欠格 民法974条)、近しいご親族にお願いすることはできません。
(2) 遺言者の意向を確認します
証人3人が同席する場で、遺言者の意向を確認します。
その場合には必ず「遺言内容を筆記した書面」が必要となります。口授より前に筆記した書面が存在してよいかという点が問題となりますが、前もって通常の遺言作成の委任を受けていて、直接ないし間接的に遺言者の意向を聞いて確認しているような場合には、その内容に即した文書を予め用意をしておくということは可能です(このようなケースで、口授と筆記が逆になってもよいと判断した例があります)。一からその場で書面を作成するのではなく、予め書面が用意してある場合の意向確認は、書面を閲覧させたり、読み上げたりする方法で行う方法も可能です。
ただし、遺言者は、必ず「口授」という方法で意思を表明しなければなりません。「口授」とは口頭で言葉を発することであるので、単に読み上げられた内容に頷くという動作だけの反応では、「口授」にはなりません。「いいです」といった簡単な言葉でも構いませんが、遺言者の意向を確認できる「口述」が必要です。
(3) 証人3名の署名押印
証人3人は、遺言者が表明した意向と筆記内容が合致していることを確認し、通常は、住所と氏名を記載して押印します。証人3人にはあらかじめ自身の印鑑を持参してもらう必要がありますが、実印である必要はありません
(4) 家庭裁判所への確認請求、その後の容態の変化に応じた遺言書の作成
20日以内に家庭裁判所に申立をしなければ、そもそも効力は発生しません。
また遺言を作成した後に容体が回復した場合には、その後6か月生存し続けた場合には失効してしまいますので、その後回復して、自書や、公証人による意思確認ができる状態にまで回復したのであれば、直ちに、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の作成に取り掛かる必要があります。
4. 有効・無効の裁判の傾向
家庭裁判所の確認は、危急時遺言の有効性について判断するものではありません。したがって、家庭裁判所による確認の通知が行われたからといって、危急時遺言の有効性が確定するわけではありません。
相続人の誰かが作成された危急時遺言の有効性を争う場合は、その有効性は、自筆証書遺言・公正証書遺言等、他の通常の形式の遺言と同様、訴訟で決着することになります。
危急時遺言が行われるのは、死期が差し迫った状態ですので、「遺言能力」「口授能力」「口授の存否」が争われることが多いと思われます。
危急時遺言は、死期の差し迫った状態で緊急的に行われるという性質上、通常の状態の明瞭・明確な意思表明までは求められず、ある程度緩めてもよいという見解もあります。
ただ、「遺言能力」「口授」は必ず存在する必要があるため、カルテ等によって、遺言当日の状態が、判断・意思表明できる程度であったと立証できる必要があります。
問いかけに反応しない・反応が鈍い、言葉を発するがその内容が不明瞭で判断できないという状態で、全くの寝たきりのため頷く等の肯定の意思表明もできない、といったケースで、読み上げに対し「あ~」「う~」という反応を示す程度であると、「遺言能力」「口授」「口授能力」の存在は否定され、無効となると思われます。
こちらの呼びかけや書面の読み上げに対し、遺言者が「いいです」「お願いします」といった意思表明をしたというケースでは、有効となりうるでしょう。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
虎ノ門法律経済事務所の弁護士コラムのページへようこそ。
弁護士相談・法律相談を専門とする虎ノ門法律経済事務所では、遺産相続の解決事例も豊富であり、お客様それぞれのお悩み・トラブル内容に沿った弁護士をご紹介することで、トラブル解決の最後までスムーズに進めることを目指しております。
遺産相続だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。