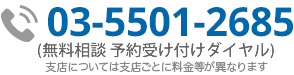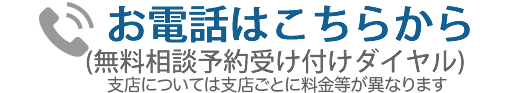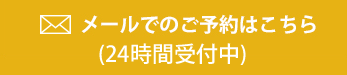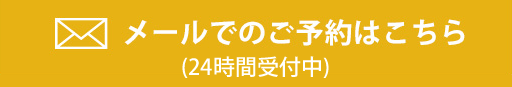2022.09.09
自己破産は2回目以降も可能?注意点や免責の条件も解説
弁護士 丸山 智史
目次
2回目以降の自己破産は可能
破産を希望されるご相談者に「自己破産に回数制限はないですよ。」とお話しすると驚かれることがあります。
2回目以降の自己破産の注意点
確かに、破産法上には、自己破産には回数制限を規定したものはありません。しかしながら、簡単に免責を認めては、債務者にとって甘すぎることにもなります。
そこで、破産法では、裁判所で免責決定を受けてから7年間は、再び免責の申立があっても、免責不許可事由(破産法252条1項10号イ)として原則免責を認めないものとしています。
そうすると、裁判所で免責の決定を受けてから7年間は、再び免責を受けることはできないのでしょうか。
2回目以降の自己破産が認められるには
一方で、破産の免責許可決定の要件には、「裁量免責」(破産法252条2項)という制度があります。
「裁量免責」とは、裁判所があらゆる事情一切考慮して総合的に判断した上で、たとえ免責不許可事由に該当する場合であっても、免責が許可決定できるつまり免責を認める制度です。
破産法第1条には、破産の目的として「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」と定められています。
そもそも破産の制度は、自らの努力では返済できない場合に、経済的な再生の機会を与える制度ですから、単に免責不許可事由に該当しているから免責を認めないとすることは自己破産の目的に反するといえます。
そのため、破産制度の趣旨・目的から、仮に免責不許可事由に該当する場合であっても、免責許可決定を受けられるよう救済制度を設けることにしたのです。
裁量免責が認められる要件
裁量免責が認められる要件に関しては、破産法には「破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して」(破産法252条2項)としか規定していません。
② 破産申立に至った経緯・事情
③ 債務者の態度・協力姿勢
④ 債権者の事情
⑤ 債務者の経済的な再生の機会の可能性
上記の観点などから、破産法1条の目的に鑑みて、免責による破産者の経済的再生を図ることが破産者自身にとっても、社会的にも好ましくないと判断される場合に限り、免責を不許可にすることが適切であると思われます。
2回目以降の破産について
自己破産の制度に回数制限はありませんので、2回目でも3回目の破産であっても、免責が認められること自体は可能です。
また、裁判所で免責決定を受けてから7年間以内に再び免責を受ける場合であっても、裁量免責制度により、免責を受けることは可能です。
しかしながら、裁判所としても簡単に破産を認めるわけにはいきませんから、2回目以降や裁量免責が問題となる案件の場合には、裁判官や破産管財人による上記①~⑤を含めた厳しいチェックが行われます。
そのため、2回目以降や裁量免責が問題となる案件の場合には、初回の破産よりも、費用も時間もかかり、破産手続前に破産審尋が行われ、裁判官が破産者から直接詳しい事情を聴取する等免責が認められるハードルが格段に高くなることに注意が必要です。
また、裁判所は、多くのケースで、同じ免責不許可事由では裁量免責を認めない傾向にありますので、2回目以降の破産に関する経緯や事情に関しても重要な判断材料となります。
2回目の自己破産が出来ない時の対処法
2回目の自己破産が難しい場合には、別の方法として債務整理や民事再生(個人再生)を行うことになります。
債務整理とは、債権者と交渉を行い、過払い分の請求や利息分をカットし、借金の減額や支払方法を変更するなどの方法により、借金を整理する手続きです。
債務整理は、裁判所を通じて行う手続きではなく、債権者との話し合いで行われますので、自己破産の回数や借入の理由を問わず、行うことができます。
ただ、債務整理は、過払い分の請求や利息分のカットがメインですので、過払い分がなければ返済額の大幅な減額は期待できません。
また、債務整理はあくまで債務を継続的に返済をすることを前提にしている手続であるため、借金額が多く、減額後の返済が難しい場合には適さないことになります。
※詳細は【任意整理】をご覧ください。
個人再生とは、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、3年から5年にかけて債権者に返済するよう再生計画を立てて、その再生計画に従って返済を行う手続です。個人再生手続も自己破産と同じく裁判所を通して行います。
民事再生の利点は、自己破産の場合にはマイホームや車を没収されてしまう可能性がありますが、民事再生であれば家や車を残しながら、無理なく返済をすることも可能です。
民事再生(個人再生)のデメリットとしては、債務額が5000万円を超える場合にはできない(住宅ローンは除きます)ことや継続的または安定した収入が見込めることが必須であることです。
民事再生も継続的に債務を返済することを前提にしている手続ですから、あくまで継続的な計画の下で返済を行うことが前提になりますので、ご注意下さい。
※詳細は【個人再生】をご覧ください。
2回目以降の破産は、当事務所にご相談ください。
2回目以降でも再び破産すること自体は可能ですが、免責を得るためのハードルは格段に上がりますし、それも裁判所で免責決定を受けてから7年間以内に再び免責を受ける場合であれば、容易には免責が受けられない傾向にあります。
2回目以降の破産の申立を行う際には、確実に免責を受けられるよう事前の対策と検討が不可欠になります。
虎ノ門法律経済事務所では、破産に精通した弁護士が多数在籍しており、2回目以降の自己破産のご相談も数多くお受けしております。
2回目以降の破産をご検討している方は、是非一度当事務所にご相談下さい。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
虎ノ門法律経済事務所の弁護士コラムのページへようこそ。
弁護士相談・法律相談を専門とする虎ノ門法律経済事務所では、借金問題・債務整理の解決事例も豊富であり、お客様それぞれのお悩み・トラブル内容に沿った弁護士をご紹介することで、トラブル解決の最後までスムーズに進めることを目指しております。
借金問題・債務整理の弁護士・法律相談の対応だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。