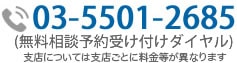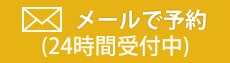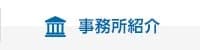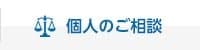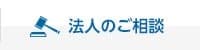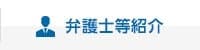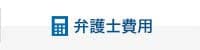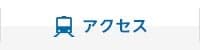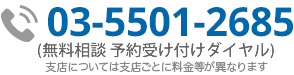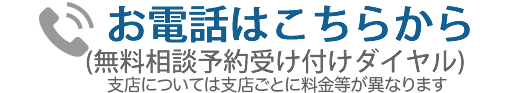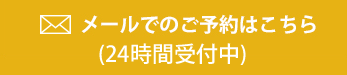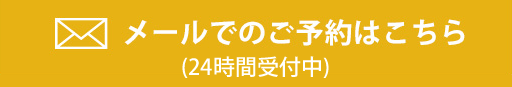2024.04.10
遺産相続の手続の期限とは?過ぎた場合の対応方法や注意点まで弁護士が解説
相続が発生した場合、自分が相続人となったことを知った人は、相続を「承認」するか、相続を「放棄」するかを選択することになります。現実には、多くの場合、相続を承認して、相続人同士で遺産分割協議を行い、例外的に、マイナスの財産が多いときなどに相続の放棄を検討する、ということが通例です。
相続を承認する場合・放棄する場合のいずれにおいても、様々な手続を行う必要があります。その中には、行うべき期限が決まっているものが多くあります。
以下では、期限のある手続・期限のない手続を紹介するほか、期限内に手続をできなかった場合のデメリットなどを紹介します。
1. 遺産相続の手続の期限とは
【相続手続の期限はいつから始まる?】
遺産相続の手続に期限がある場合、その期限のカウントダウンは、いつから始まるでしょうか。
各手続の内容については後に詳しくご説明しますが、限定承認、準確定申告及び相続税の申告など多くの手続においては、(被相続人が亡くなった日そのものではなく、)「自分のために相続があったと知った日」が、期限のカウントダウンの始まる日となります。
以下では、相続を承認する場合と放棄する場合とに分けて説明します。
【相続を承認する場合】
(1) 期限のある手続:限定承認 → 3ヶ月
被相続人の財産状況によっては、プラスの財産(預貯金や株式、貴金属など)とマイナスの財産(借金など)とのどちらが多いか分からない場合があります。
限定承認は、そのような場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。
限定承認は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
ただし、限定承認は相続人全員で申立てをする必要があることもあり、利用されるケースはそこまで多くありません。
(2) 期限のある手続:準確定申告 → 4ヶ月
被相続人が自営業者であったり家賃収入・株式配当があって所得があったりする場合、被相続人の死亡した年の所得税を申告する必要があります。この手続を「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、管轄の税務署で行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税がかかってしまうので、注意が必要です。
準確定申告は、各相続人が共同で手続をしてもよいですが、1名の相続人が他の相続人の氏名を付記して代表で手続を行うこともできます。
ただし、もし被相続人について、死亡した年の所得が所得税の発生しない範囲内であった場合には、準確定申告は必要ありません。
(3) 期限のある手続:相続税の申告と納付 → 10カ月
相続税は、相続した遺産の額に応じて発生する税金です。
相続した財産のうち、正味の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税が発生し、納付をしなければなりません。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月の期限内にする必要があります。
相続開始を知った日から10カ月以内に相続税を申告しないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減・猶予制度が利用できなかったりするというデメリットが発生しますので、注意が必要です。
(そのような事態にならないよう、安全策として、「被相続人が死亡した日から10カ月」を実際上の期限として申告の準備を進めることが多いです。)
(4) 期限のある手続:(遺留分を侵害された場合)遺留分侵害額の請求 → 1年
遺留分は、配偶者や子ども、また親や祖父母といった相続人が、最低限相続できる金額と割合のことです。
遺言がある場合に、遺言どおりに遺産を分割すると十分に財産を取得できない法定相続人が、自己の利益(遺留分)を侵害されてしまうことがあり得ます。遺留分の権利は、そのような場合に、遺留分を侵害された相続人が、侵害している人に対して、自らの取り分を請求することによって行使します。これを、遺留分侵害額の請求といいます(民法の改正前は「遺留分減殺〔げんさい〕請求」と呼ばれていました)。
遺留分侵害額の請求は、相続の開始と遺留分の侵害の事実を知った日の翌日から1年間の期限内に行う必要があります。
(5) 期限のある手続:不動産の相続登記(2024年4月1日以降) → 3年
2024年4月1日から、土地や家といった不動産を相続した場合に、相続登記をすることが義務化されます。改正された不動産登記法が2024年4月1日から施行されることによるものです。
具体的には、遺産である不動産を取得した場合、相続開始を知り、なおかつ遺産である不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、その不動産について相続登記を行わなければなりません。
この不動産の相続登記の義務化は、2024年4月以後に遺産である不動産を取得した場合だけでなく、2024年4月以前に取得した場合にも適用されることに注意が必要です(ただし、2024年4月以前に相続したケースでは、2027年3月末まで猶予期間が認められます)。
3年以内に相続登記をしない場合、法務局から登記申請を促す催告が送られてきます。その催告に正当な理由なく応じない場合、裁判所が10万円以下の過料を科すという仕組みとされています。
法務省によると、正当な理由としては、以下の場合などが想定されています。
② 遺言の有効性や遺産の範囲などについて、相続人の間で争いがあるため、誰が不動産を取得するか明らかにならない場合
③ 相続登記の義務を負う人に、重病やこれに準ずる事情がある場合
④ 相続登記の義務を負う人がDVの被害を受けており、その生命や心身に危害が及ぶおそれがあって、避難を余儀なくされている場合
⑤ 相続登記の義務を負う人が経済的に困窮しているため、登記申請を行うための費用を工面できない場合
【相続を放棄する場合】
(6) 相続放棄 → 3ヶ月
被相続人の遺産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合や、どのような財産が残っているのか不明で相続をしたくない場合には、「相続放棄」をすることができます。
相続放棄を行うと、プラスの財産も相続できない反面、マイナスの財産も一切相続せずに済みます。
相続放棄は、相続開始があったことを知った日の翌日から3カ月の期限内に、家庭裁判所に申し立ての書類を提出する方法によって行います。
2. 遺産相続の手続の期限を過ぎてしまった場合
相続手続を期限内に行わなかった場合、いくつかのデメリットが生じます。以下、具体的にどのようなデメリットが生じるかを説明します。
(1) 税の軽減・猶予制度の適用が受けられなくなる
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内と定められています。この期間内に遺産分割協議が成立しない場合もありますが、そのような場合でも未分割であるとしていったん法定相続分で分割したと仮定して相続税の申告と納付を行うことになります。もし、申告と納付を適切に行わないと、税金の軽減・猶予制度が利用できなくなります。
代表例として、以下の制度が利用できなくなります(順不同です)。
② 農地等の納税猶予の特例
③ 小規模宅地等の特例
(2) (相続税の申告の場合)延滞税がかかる
相続税を申告期限までに納付しないと、完納までの期間、延滞税が発生します。延滞税の利率は、納期限から時間が経つことによって変化(上昇)していきます。
(3) (不動産を相続した場合)過料に処せられる
上述のように、2024年4月以降は、不動産を相続した場合に、3年以内に相続登記をしないと、法務局から登記申請を促す催告が送られます。その催告に正当な理由なく応じないでいると、10万円以下の過料を科せられることがあります。(詳細は、上記「1.(5) 期限のある手続:不動産の相続登記(2024年4月1日以降)」をご覧ください。)
(4) (相続放棄の場合)3カ月以内に放棄をしないと、相続を承認したものとみなされる
相続放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に行わないと、相続をすべて承認したものとみなされます。そうなると、マイナスの財産がどれだけたくさんあっても、それらをすべて承継しなければならなくなります。
3. 期限のない遺産相続の手続とは
(1) 遺産分割協議
相続人の全員の話し合いによって被相続人の遺産の配分を決めることを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議には、特に期限はないので、基本的にはいつ協議が成立しても問題はありません。当事務所においても、1年や2年で終わらず、まれに非常に複雑な事件では5年以上の期間に渡り継続している遺産分割協議の事件があります。
ただし、協議がまとまらない間に被相続人の死後10カ月が経ってしまい、相続税の申告期限が来てしまうことがあります。(その場合の対処法は、上記「2.(1) 税の軽減・猶予制度の適用が受けられなくなる」をご覧ください。)
(2) 預貯金の解約・名義変更
被相続人の預貯金を解約して払い戻すことには、特に期限がありません。ですので、遺言で相続人が指定されているときは受取人とされた人が、遺産分割によって相続人を決めたときはその相続人が、金融機関で解約の払戻しを行います。
ただし、10年放置してしまうと休眠預金として扱われ、引出しに人手間かかることになります。
4. 遺産相続に関することで困っている方へ
以上のように、相続の手続には、期限の決まっているものと期限のないものとがあり、期限があるものについてはそれを守らないとデメリットがあります。
弁護士に相談をすれば、今後の見通しやいま自分がやるべきことを知ることができるようになります。
被相続人がお亡くなりになって、いつまでに何をすればよいのかわからないときは、ぜひ当事務所にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
虎ノ門法律経済事務所の弁護士コラムのページへようこそ。
弁護士相談・法律相談を専門とする虎ノ門法律経済事務所では、遺産相続の解決事例も豊富であり、お客様それぞれのお悩み・トラブル内容に沿った弁護士をご紹介することで、トラブル解決の最後までスムーズに進めることを目指しております。
遺産相続だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。